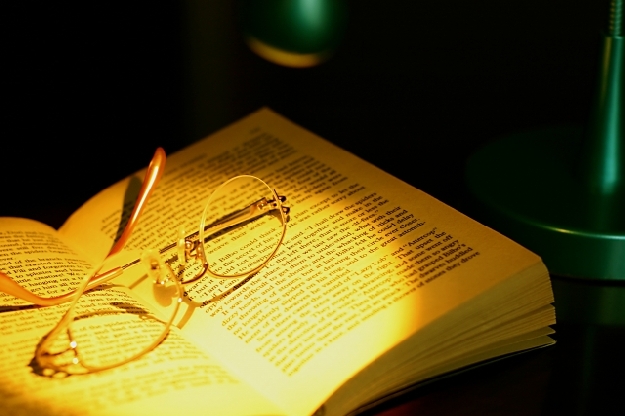| 新しいあなたへ~新シリーズ「ココロの処方箋」~ヘッセの言葉⑧~ |
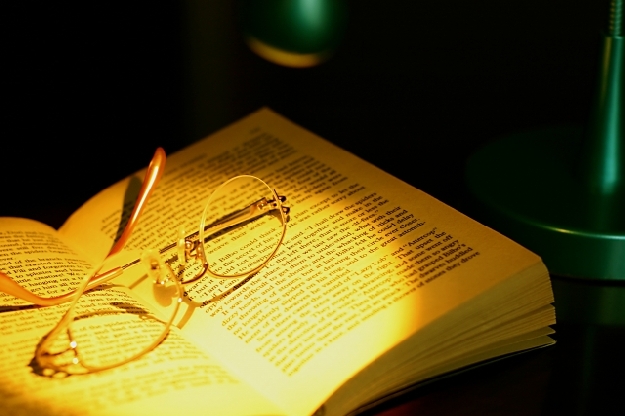
雨の多い今年の秋ですね。
運動会が何度も流れてしまったり、体育館での開催になったり。
遠足の日程が何度も変更になったり…。
それでも、「晴れ率」が高いとされる文化の日(過去40年で、雨の日はたったの2回(東京)という確率だそうです!)あたりからは、晴天率も高くなり、ようやく秋の行楽を楽しめている方もいるのではないでしょうか。
見上げれば、秋特有のちれぢれの雲が、ランプシェードのように日の光を芸術的な明かりに変えています。
ヘッセは、雲を愛していました。
「私の罪は、人よりも天空をさすらう雲を愛したことだ」
と、述懐しているほど、雲に魅了された詩人だったのです。
季節は冬に向かっていますが、まだ晩秋の季節は続きます。秋の夜長・・・の第二弾、今回は読書について、ヘッセとともに考えてみたいと思います。
読者のみなさん、本はお好きでしょうか?最近は、電車の中で本を読む人を見かけることが珍しい光景とさえなってしまいました。
本と一口に言っても、kindleなどの媒体で文章を読めるわけですから、スマートフォンを見ている方が必ずしも本を読んでいない、というわけではないのでしょう。
けれども「紙」の本は格別です。気に入ったところに印をつけたり、書き込んだり。折ってみたり。その時の筆跡や経年した紙の質感は、読み返したときに新たな気付きを与えてくれることもあります。そして何より、めくるときのあの手触り。どんなにITが進化しても、本が世の中から消えることはないと思います。
ヘッセにとっての「本」とは、どういうものでしょうか。
どんな書物を読んだとしても、古今東西のあらゆる書物を一冊残らず読んだとしても、それゆえに幸福になるということはない。
けれども、自分が読んだ本は必ず自分に力を与えてくれる。
迷ったとき、いざというときに本来の自分に立ち戻れる力と、その力を育む栄養をひそやかに与えてくれているのだ。
(詩「書物」)
文章を書くことを生業にしている私が言うのも今さら、という感じではありますが、私は小さいころから本を読むのが大好きでした。文字だけで繰り広げられる本の世界に、自分だけの色や風景、登場人物の外見などを創り上げていきます。同じストーリーでも、きっとこの「イメージ」が違うだけで本の印象は全く異なるでしょう。そして、読者一人ひとりの心に響く言葉も、シーンも違う。読書の醍醐味です。
大学で文学部を卒業した後、すぐに入社した会社は、当時「大手航空三社」と呼ばれていたうちの一社の、子会社でした。子会社と言えども、大手の看板を背負っています。社員も親会社からの出向者も多く、優秀で楽しい社員の方に恵まれ、楽しい新社会人生活を送りました。
そのときの入社試験の最終面接で、役員の方が、面接で読書についてたくさんの質問をしてくれました。自分の思いや勉強してきたことを肯定してくれた思いで、嬉々として返答したことを覚えています。
いざ、合格通知をもらい、入社してみると、自分の部署の担当役員が、件の面接官でした。
けれども、不義理なことに、私は海外勤務を夢見ていて、一年で同社を退職、ドイツへ渡るという選択をしました。
そんなときに、あの役員が私にこう言ってくれたのです。
「ドイツへ行きたいという君をとめたりはしない。けれども、ただドイツ語が話せる人間になりたいのだったら、考えなさい。言葉を話せるということは素晴らしいが、もっと素晴らしいのは、語る内容がある人間だ。君がいつか面接で本についてたくさん語ってくれたように、語るべきことにあふれている人生を送りなさい」
私は、本の力の偉大さに改めて気づかされました。
知らずのうちに、私は大手企業の役員から背中を押してもらえる新人になっていたのだ、と。
それが、小さいころから時間も忘れて読みふけっていた本たちのおかげだったのだ、と。
ドイツにも、愛読書を持って旅立ちました。
それから数社企業を渡り歩いたのちに、たどり着いたのは、文筆家という文章の世界でした。
私の場合は、たまたま本の道に足を踏み入れましたが、そうでなくても、本はあなたに大きな力を与えてくれます。
きっと、読者のみなさんも、琴線に触れた本や文章に、一度は出会ったことがあるのではないでしょうか。そして、心が救われたり、元気をもらえたり、考え直すきっかけをもらったり。そんな経験もきっとあるでしょう。
今、世の中には、たくさんの本があふれています。その中で「とっておきの一冊」を見つけることはとても難しいですね。
私が本を買う場所は3か所です。実用書は、本屋さんとネットショップ。そして、小説や評論、詩集などの文芸書は、本屋さんと、じつは半分以上が古本屋さんで買っています。
それには、理由があります。
本屋さんには、「売れている本」しか売っていないからです。私は、売れている本にはあまり興味がありません。というよりは、「みんなが好きな本」=「自分が好きな本」とは限らないと思っているのです。
もちろん新刊で素晴らしい本に出会うこともありますので、本屋さんにいれば一日過ごしてしまえるほど好きですが、古本屋さんで売れる売れないにかかわらずじっくり一冊一冊吟味して本を買う方が、「自分に合った一冊」に出会えることが多いのです。
ヘッセの言葉が、私の考えを後押ししてくれます。
読書にもビジネスと同じような効率や最大効果を狙って、評論家の推薦する図書や流行している本を読むならば、結果的にかえって非効率で効果は薄くなるだろう。
それよりも、自分の内なる心が欲しがるままに、あるいは自分の感性が察知するままに、気に入った本を選んでじっくりと読んだほうがずっとマシだ。
そういう自然体の読書こそ、本当に自分の教養として身につくものだからだ。
(「書物とかかわること」)
どんな本が自分に合っているかわからない、という方もいるでしょう。
そんな方は、好きな生き方をしている、考え方に共感が持てる、内面が魅力的だと感じる。そういう友人知人におススメの本を教えてもらうのも良いかもしれません。
読書経験を積み重ねていけば、どれが自分の心に触れる本なのか、次第にわかってくるようになります。
自分の好みの本がある-。
なんだかとっても大人の雰囲気がありますよね。
秋の夜長に読書。その光景にふさわしい大人の女性になりたいものです。