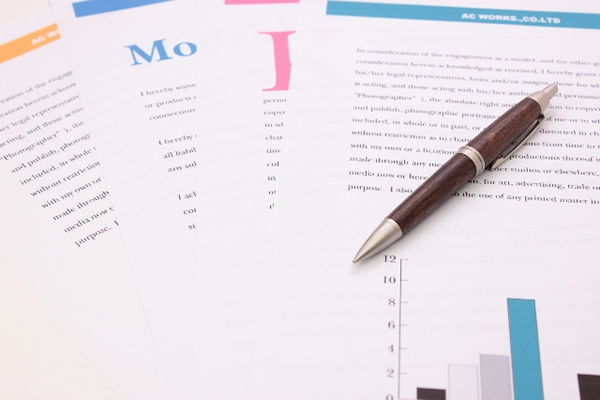| 古典落語de「心をつかむ企画提案とは?」 |
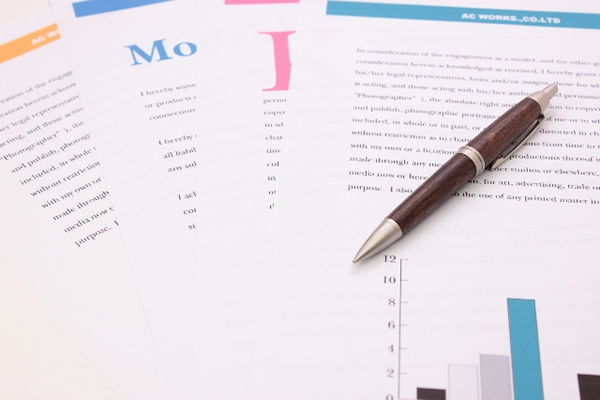
ビジネスには、企画提案がつきものですよね。日頃、頭を悩ませていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
実は古典落語の中に、「企画コンペ」の一部始終を描いたような噺があるんです! そこには、クライエントの心をつかむ企画提案のポイントが隠されているかもしれません。
大きな商家の主人、赤螺屋吝兵衛(あかにしや けちべえ)さん。名前の通り大変な締まり屋です。
彼の目下の心配事は、自分の死後。跡を継いだ者に贅沢をされて、せっかく作った身代を潰されてはかないません。
3人の息子のうち、誰に継がせたらいいだろう…。
考えに考えた吝兵衛さん、息子たちにあるイベントの企画を提案させ、どのようにお金を使うのか確かめることを思いつきます。
そのイベントとは、なんと吝兵衛さんのお葬式。自分自身のお弔いをテーマに、企画コンペをしようというのです。
まず呼び出されたのは長男です。
「私は立派な、ごく盛大な弔いをしとうございます。私が仕切っていながら、後で世間様から笑われるようでは悔しゅうございますから」
こう切り出した長男、それはそれは絢爛豪華な葬儀の案を並べます。
お通夜は2晩。葬儀会場は増上寺か本願寺を借り切って、お坊さんを22人ほど祭壇の左右にずらりと並べます。
2000人を上回ると見込まれる参列者には豪華な仕出し料理とお酒を出し、ひとり一人にお土産(本塗り三段重箱入りお弁当)やお車代を準備。香典返しには舶来の金時計を…。
「いい加減にしろ! 人の金だと思ってじゃんじゃん使いやがって!」
すっかり不機嫌になった吝兵衛さんは、次男を呼び出します。
「あっしゃあ、そんじょそこらの弔いじゃ嫌だね。弔いの歴史に残る、皆がびっくり仰天する破天荒な弔いがやりてぇんだ。そうだねぇ、色っぽい弔いがいいや!」
そう言うと次男は、「色っぽい弔い」について熱く語り出します。
家々の塀に紅白の幕を張り巡らし、威勢の良いお囃子が鳴り響く中、葬儀がスタート。
いなせな鳶頭の木遣りを先頭に、手古舞姿の芸者衆50~60人の粋な行列が葬儀に華を添えます。
その後ろを吝兵衛さんのからくり人形を乗せた豪華な山車、吝兵衛さんのお骨が入った御神輿と続き、「チョーン」と木が入ったところで葬儀委員長の弔辞が…。
「まるで町内の祭りじゃないか!」
ますます不機嫌になった吝兵衛さんは、三男を呼び出します。
「弔い、どうしてもやります?」 兄ふたりとはうって変わって消極的に切り出した三男。「やるならなるべくお金をかけずに」という彼のプランは、実に驚くべきものでした。
弔問客に出すのは、おせんべい(中元・歳暮のもらい物を活用)とお茶のみ。
出棺は、早朝4時半(出棺時に参列者がいなければ、お茶やおせんべいを出さなくて済むから)。
お棺は「どうせ燃やしてしまうんだし、多少臭くても…」ということで、漬け物樽で代用。
ご遺体を入れたら隙間に新聞紙を詰め、その辺に落ちている板っきれを打ち付けて蓋をします。
お棺(に見立てた漬け物樽)を運ぶ際には、荒縄で縛って棒を通して2人で担ぎます。
ここまできて、ひとつ問題が発生。
「先棒は私が担ぐとして、後棒はどうしても人足を雇わなければなりませんねぇ…」
こうつぶやく三男に、嬉々として吝兵衛さんが一言。
「心配するな、後棒はおとっつぁんが担いでやる!」
自分の弔いであることも忘れて、人件費節約のために三男と2人でお棺(漬け物樽)を担ごうという吝兵衛さん。この三男にならば、安心して身代を譲ることができそうですね。
一般に、大きな商家であれば長男の提案を評価するのが普通ではないかと思います。
いわば大会社の社長のお葬式ですもの、会社のメンツにかけて恥ずかしくないものにしよう、関係者の皆様に失礼のないものにしよう、と考えるのは当然のように思えます。
でも、吝兵衛さんは違うんですね。
メンツや見栄よりも、実を取るタイプ。「葬式なんぞに過度にお金をかけるのはばかばかしい」という考えなのですから、長男とは真逆です。
長男は吝兵衛さんの(かなり変わった)本当の望みについては汲み取ることなく、考慮もしていなかったということになります。結局は世間体や見栄を重視して、「自分がやりたいこと」を提案してしまった、ということでしょう。
次男はどうでしょうか。
彼の企画、実は私は大好きです。だって面白いじゃありませんか、「色っぽい弔い」なんて。世が世なら、個性的な葬儀形態としてどこかの葬儀社が採用しそうな、ユニークなアイディアです。
でもやっぱり、吝兵衛さんの求めているものとは違ったんですね。
次男も吝兵衛さんの思いとは裏腹に、自分自身の好みやアイディアを重視して、やっぱり「自分がやりたいこと」を提案してしまった、ということになるでしょう。
結果的に吝兵衛さんの心をつかんだのは、三男でした。
三男の提案、常識的に考えたら「いや~、これはないわ~」ですよね。
でも吝兵衛さんにとっては、この上なくすばらしいものだったんです。お金の使い方に関する価値観が一致している上に、具体策も「実を取る」、「コストカット」という観点でみたら、非常によく工夫されているのですから。
三男坊は日頃からお父さんの言動をよく見ていて、お父さんが何を求めているかを理解していたのでしょうね。
こうしてみると、何かを他者に提案したり売りこんだりするときの秘訣って、結局は「相手方思考」なんだとつくづく思います。
真に「相手がやってほしい(であろう)こと」にこだわり、徹底的に考え抜くこと。視線を自分ではなく、相手に向けること。これに尽きるのではないかなあと思います。
ごくごく当たり前のようで、実現しようとするとなかなか難しいものですけれどもね。
いつも心にかけておきたいと思います。
さて、この噺の聴きどころをご紹介しましょう。
私がおススメするのは、何と言っても次男のプレゼンの場面です。「色っぽい弔い」のデモンストレーションが秀逸!
お囃子をスキャット風に表現したり、山車の上の人形の形態模写をしたり、架空の弔辞を読み上げたり…。「色っぽい弔い」の様子や楽しさ(笑)が、手に取るように分かります。
爆笑しながらも、「情熱的で人を引き付けるうまいプレゼンだなあ」と感心することしきり。ここが落語家さんの腕の見せどころでもあります。
心をつかむ企画提案の秘訣のみならず、プレゼンテ―ションに関しても学ぶところの多い古典落語、「片棒」。
ぜひ聴いてみてくださいね!
おススメCD:「宮戸川・片棒・野晒し」/志ん朝初出し <七>(ソニー・ミュージックダイレクト)